高圧電気取扱特別教育を修了すると何ができる?受講内容や資格の活かし方まで徹底解説2025.08.29

電気工事のなかでも、高圧を取り扱う業務に携わる場合に受講が義務付けられているのが「高圧電気取扱特別教育」です。
一方で「電気工事士として働きたいけれども、高圧電気取扱特別教育を受けるべき?」「受けると何ができる?」といった疑問を持つ方もいるかも知れません。
今回の記事では、高圧電気取扱特別教育の概要や修了するとできるようになる作業内容について解説します。
高圧電気取扱特別教育の受講内容や活用方法についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
高圧電気取扱特別教育とは?法律上の位置づけと目的を解説

高圧電気取扱特別教育とは、正式名称「高圧電気取扱作業者教育」と呼ばれ、「高圧の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理もしくは操作の業務を行う人」を対象とした講習のことです。
高圧とは直流では750ボルト、交流では600ボルトを超え、7000ボルト以下の電圧のことです。高圧電気は電力会社の発電所から直接供給されるため、需要家側で必要な電圧に変圧するために、受変電設備(キュービクル)を設置します。自社側で変電と分電両方を行うことで、停電や電圧の降下が起きにくく、電力を安定的に供給できるのが特徴です。
また、低圧電力よりも単価が安くコストパフォーマンスが良いため、大量の電力を消費したり、停電リスクを減らしたりといったニーズのある病院やデータセンター向けの電気と言えるでしょう。
メリットが多くある一方で、高圧電気には労働事故発生のリスクが高いことから、業務上では正しい知識と適切な行動によって取り扱うことが重要です。
そのため、労働安全衛生法第6章「労働者の就業に当たっての措置・第59条第3項」にて、高圧または特別高圧を取り扱う場合には高圧電気取扱特別教育の受講を義務付けています。
高圧電気取扱特別教育を修了すると何ができる?具体的な作業内容
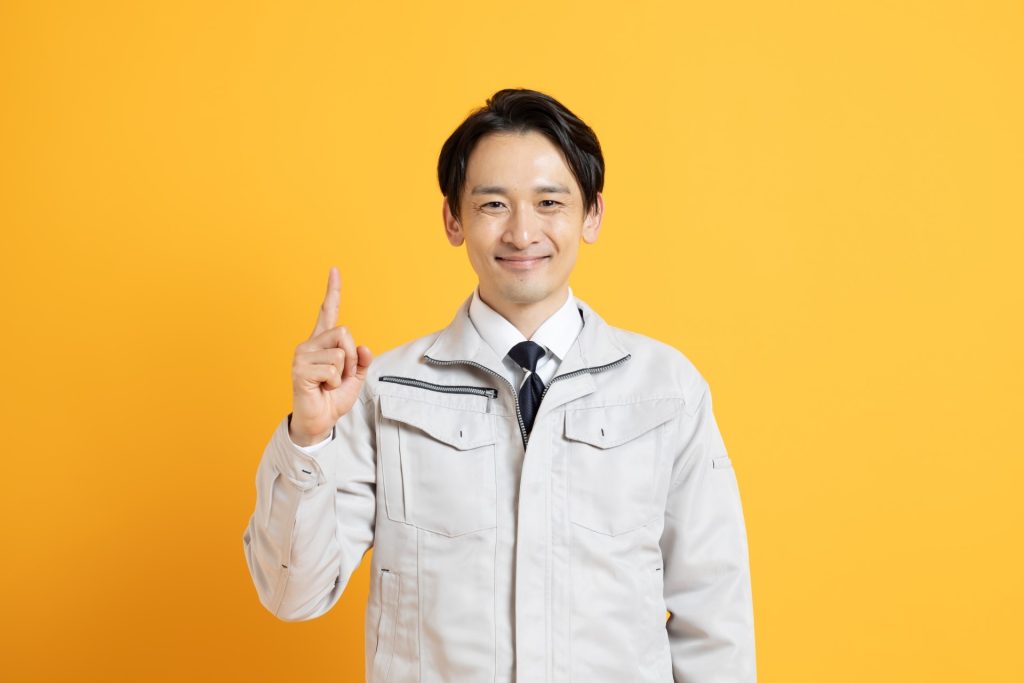
高圧電気取扱特別教育を修了することで、高圧(直流(DC)では750V、交流(AC)では600Vを超え、7000V以下の電圧)を取り扱う業務に従事できるようになります。具体的な高圧電気取扱特別教育を修了することでできる作業や業務内容を順に解説します。
高圧活線作業・活線近接作業
活線とは、電力が供給されている状態の送配電線のことです。電力が流れている状態の総配電線は、当然ですが感電などの危険性が高まっています。高圧電気取扱特別教育を受けていることで、絶縁保護具を装着した状態での高圧の活線の修理や近くにある状態での作業ができるようになります。
高圧活線作業用器具の使用
活線作業には、以下のような耐圧性の高い絶縁棒を使用します。
・高圧カットアウト操作棒:充電中の高圧カットアウト(高圧の配電路の開閉、変圧器の一次側に設置しての開閉動作、過負荷保護用の高圧開閉器など)操作時に使用
・断路器操作用フック棒(ディスコン棒):断路器(電力回路の無負荷時の電圧開閉に使用する電力機器、遮断器)や負荷開閉器を操作するのに使用
・間接操作用棒(ホットスティック):充電された高圧電路などを活線のまま工事を行う場合に使用、先端に各種器具(ペンチ・ドライバー)を取り付けての作業が可能
高圧活線作業用の器具を使用する際にも、高圧電気取扱特別教育の修了が必要です。
高圧電路の停電作業と安全確認
停電時の高圧電路の修理や点検、安全確認に関する作業も高圧電気取扱特別教育の受講が必要です。
高圧電気取扱特別教育の受講内容と時間

高圧電気取扱特別教育は、法律で定められた内容を受講し、修了する必要があります。高圧電気取扱特別教育の受講内容や時間を以下の一覧にまとめました。
| 区分 | 受講する内容 | 所要時間 |
| 学科 | 高圧または特別高圧の電気に関する基礎知識 | 1.5時間 |
| 高圧または特別高圧の電気設備の構造および取扱いの方法 | 2時間 | |
| 高圧または特別高圧用の安全作業用具に関する知識 | 1.5時間 | |
| 高圧または特別高圧の活線作業および活線近接作業の方法 | 5時間 | |
| 関係法令 | 1時間 | |
| 実技 | 高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 15時間以上 |
| 充電電路の操作の業務のみを行う者の場合 | 1時間以上 |
学科はいずれの作業や業務内容でも共通ですべての学科の受講が必要です。一方実技は実際に携わる作業や業務内容によって所要時間が異なります。
高圧電気取扱特別教育は、働いている事業所で開催される講習を該当者が受けるほか、学科や実技は関東電気保安協会やCIC日本情報建設センターなどの関連団体で開催している高圧電気特別教育講習会に個別で申し込んで受講する方法もあります。
高圧電気取扱特別教育と他の電気関連資格との違い

高圧電気取扱のほかに特別教育と名前の付く講習や、電気工事士をはじめとした電気関連資格を違いを踏まえて順に解説します。
低圧電気取扱業務特別教育
低圧電気取扱業務特別教育とは、契約電圧が交流(AC)600V以下、直流(DC)750V以下の低圧電気を業務上で取り扱う際に受講が義務付けられている特別教育講座です。
低圧は、地域の電力会社の発電所から供給された電気が変電所で変圧され、柱上変圧器(トランス)を通じて家庭や店舗、小規模な事業所などに供給されます。
電圧が低く特別な設備不要で供給できることからさまざまな用途に活用されている一方で、低圧電気の取扱は労働事故が発生するリスクがあるため、高圧電気取扱特別教育と同様に、特別教育の受講が義務付けられています。
特別高圧取扱業務特別教育
特別高圧取扱業務特別教育とは、契約電圧20000V以上の特別高圧を業務上で取り扱う際に受講が義務付けられている特別教育です。
特別高圧は発電所で最大50万Vまで作られ、一次変電所で15.4万Vまで変圧された電力が自社で設置した受電設備へ直接供給されます。
高圧電気よりも電圧降下や停電リスクが低く、電力も安定的に供給されるため、オフィスビルや工場、ショッピングモールなどの多くの電力を使用する施設で使用されているのが特徴です。
ただし特別高圧を利用するためには、専用の受変電設備を設置する必要があるだけでなく、維持管理に高額なコストも発生します。
電気工事士
電気工事士とは、電気設備の設置や工事などを行える国家資格です。電気工事士法という法律により、電気工事や保守点検などは電気工事士資格の所持が義務付けられています。
先程紹介した高圧電気取扱特別教育をはじめとした特別教育は、すべて規定の学科や実技講習を受けることで取得できる講座資格です。一方で電気工事士は学科試験と実技試験に合格し、所定の実務経験を積むことで取得できます。
なお、特別教育を受けただけで電気設備の設置や工事といった作業を行うことはできません。電気工事士資格を取得したうえで、自分の担当する業務や作業に関する特別教育を受けることで、所定の電気工事や保守点検、電圧電気の取り扱いが可能となります。
電気主任技術者
電気主任技術者とは、電気工事士と同じく電気事業法という法律で定められている国家資格です。電気事業法では、変電所、送電線などの電気工作物の設置者に対して、原則として事業場毎に電気主任技術者を選任し、電気設備の工事、維持および運⽤に関する保安の監督を行うことを義務付けています。
電気主任技術者は、取り扱う電圧により第一種から第三種が存在しています。
高圧電気取扱特別教育の活かし方:キャリアパスと需要

高圧電気取扱特別教育を受講し、修了することで高圧電気を取り扱う業務に携われます。病院や事業所等の重要施設の電気工事業務が可能となるため、できる業務の幅が広げられ将来的なニーズも多くあるでしょう。
ただし、高圧電気工事や保守点検などの作業には、高圧電気取扱特別教育の受講だけでなく、電気工事士資格が必須です。まずは第二種電気工事士資格取得をともに目指すことで将来的にも安定した働き方ができるでしょう。
未経験から電気工事士を目指すなら「株式会社sora」でぜひ働いてみませんか。未経験者でもしっかりとした研修を受けたうえで、業務に必要な技術を身につけながら電気工事士資格取得が目指せます。
当社の第二種電気工事士資格取得率は100%、さらに第一種も80%以上です。資格取得後は給与にも反映されるため、やりがいやモチベーションアップにもつながります。
まとめ
高圧電気取扱特別教育で安全な作業とキャリアアップを 高圧電気取扱特別教育の概要や修了するとできるようになる作業内容、受講内容、取得後の活用方法について紹介しました。
高圧電気に関する業務は今後も高いニーズがあり、将来性も高いと言えます。
電気工事士資格とともに、高圧電気取扱特別教育を修了し、さらなるキャリアアップも目指していきましょう。
